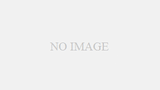こんばんは。けんちゃんです。
今回はミツバチに興味を持ち、そして花の蜜との共生関係について知りました。そして、他の生き物にも面白い共生関係があるのではないかと思い調べてみることにしました。
・アリとアブラムシ
アブラムシは植物の汁を吸い甘露(ハニーデュー)を作り出す。
アリはその甘露を吸い栄養源を得る。アブラムシは外敵から身を守ってもらうことができる。
(ここで早速だが、このような共生関係はいつから生まれたのか、そして意図的に動物たちが始めたものなのかという疑問が生じた。)
ダーウィンによって提唱された「環境に最も適した個体が生き残り子孫を残す」環境に合わない個体が淘汰され、結果的に適応した形質が残る。
この共生関係が完成したのは相当昔。化石からもありとアブラムシが共生したことが推測されている。そして、生物は自分で進化しようとおもって進化したわけではないのだ。
様々な動物の共生関係について
・クマノミとイソギンチャク
イソギンチャクはサンゴの仲間で触手に毒針を持っている。しかし、クマノミは体から特殊な粘液を分泌することで毒針に刺されることなく、職種の中に身を隠すことができる。
ここでクマノミのメリットは安全な隠れ家を持つことができる。子育ての場所を得ることができる。食べ物の供給源を得ることができる。ということがある。
そして、イソギンチャクのメリットはお掃除をしてくれる。チョウチョウウオから身を守ってくれる。排泄物から栄養を補給することができるということがある。
(イソギンチャクに関する豆知識:クマノミは群れの中で一番大きな個体がメスになる。そして次に大きな個体がオスになる)遊泳力が弱いクマノミは生息するイソギンチャクから離れるのが難しいため、限られた範囲内で繁殖機会を得るために性転換は非常に有利な戦略となる。
片利共生
アリドリとオニキバシリと軍隊アリ
軍隊アリのコロニーが移動すると、その刺激で様々な昆虫が飛び出してくる。その飛び出してきた昆虫を捕食する。
軍隊アリは巣を作らずに常に移動しながら狩りを行う。
アリドリはこの軍隊アリの移動に合わせて行動を共にする。賢いな。
0625 これについて調べる
タツノオトシゴとクラゲ
カイメンと天ぷらイソギンチャク
キンチャクガニとカニハサミイソギンチャク
ハゼとテッポウエビ
賢い習性
雀亜目の鳥:複雑な歌を囀る能力を持ち、これは遺伝ではなく、集団の中で鳥から鳥へと歌が伝承されていく。どんな流行歌があるのだろうか。歌があるなら自分も鳥に産まれるのもいいかもしれない。
AIだとなかなか面白い情報がもっと出てこないな
そしてさらに進化について興味を持った。
・自然選択
・遺伝的浮動
ボトルネック効果
創始者効果
・突然変異
があった。
この中で名前のかっこよさから、創始者効果に興味を持った。
創始者効果による進化が見られるのは
アイスランド、アミッシュ、トリスタン、だーウーニャトウ
創始者効果とは、少しの生き物が新しい場所でグループを作ると、そのグループはもといた大きなグループと比べて持っている特徴の種類が減ってしまうことがあるということである。
代表的なアーミッシュについて調べた。
アーミッシュはアメリカやカナダに住むスイスから来た昔ながらの生活を守っているキリスト教の一派である。
電気や自動車を使わず、義務教育は8年生までであり、14歳までである。
ランシュプリンガという思春期の若者が共同体の外の世界を経験する通過儀礼がある。
16歳から結婚までの間、共同体の規則から一時的に解放される。
自分だったら、読む本を制限されたり、聴く音楽を制限されたら嫌だな。今一番制限されて嫌なのは文字を書けなくなること。B‘Zの楽曲を聴けなくなること。官能的なものを見れなくなることだと思う。
動物の写真 植物や虫をとるのもいいな