こんばんは。けんちゃんです。
今回は自分が電気とガスのない生活をしてみて、昔の人はどのようにして生活していたんだろうと興味を持ち、調べてみました。
まず、自分が一番困ったことは髪が洗えず、ドライヤーで髪を乾かすことができないということです。暗いとか、暑いとかはどうでもいいのです。とにかく髪の毛を気持ちよく洗えないことが辛い。前はお風呂なんてめんどくさくて嫌だなんて思っていましたが贅沢な話です。
やはり失ってみないとそのことの大切さには気づきづらいのかもしれません。
そこで昔の人はお湯を沸かすのも今よりも大変な時にどれくらいの頻度でお風呂に入っていたのかが気になりました。そしてシャンプーではなくて何をつけて洗っていたのだろう。
江戸時代には月に1〜2回髪を洗うことがあった。シャンプーの役割を果たしたのは、ふのり、うどん粉、粘土、卵の白身、椿油の搾りかすだった。
ちょっと考えられないなと思った。全部意味がわからない。石鹸とかではダメだったんだろうか。卵の白身を使ったらもっとベタベタになってしまうような気がするのだが、、
今はシャンプーでスッキリできるから幸せだと感じる。でその当時を生きていた人からしたらなんてことないことだったんだろう。シャンプーがない代わりに色々な工夫がされていたに違いない。
他に電気とガスなしで困ったこと
洗濯機が使えない
炊飯器が使えない
暑い
食料の保存はどうしていたのだろう
灰汁がよく使われていた。釜戸で薪を燃やして出た肺を水に浸し,曽於上澄み液を利用したアクは油汚れを入荷したり短波気質を分解したりする恋かがあった各家庭に悪桶が置かれ肺を水に浸してアクを抽出していた
他にも植物由来の洗浄剤があった
(無患子の実は初めてみた文字だ。調べてみたい。)
室町時代には羽子板は胡鬼(こぎ:トンボのこと)板呼ばれていた。トンボが蚊を食べることから病気除けにつながると言われる。
無患子のみは子が患わないという意味合いで使われるこの種は羽子板の先の黒い球とひて使われてきた
羽付は子供たちが健やかに育つように厄を跳ね除けるという願いを込めて行われる正月の阿蘇びである
羽子板は古くから魔除けや厄除けの意味合いを持つ縁起物として扱われてきた。
無患子の種から無病息災,羽の形がトンボに似ておりトンボは病気を媒介するかを食べる駅中であることから正月には寝つきをすると夏になっても蚊に刺されないという言い伝えが生まれた。
羽付きのカーンカーンという音は魔物が嫌う音だと考えられていた
羽子板の起源は平安時代に宮中で行われていた毬杖遊びという悪魔祓いの儀式に由来すると言われている。


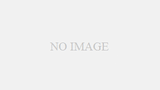
コメント